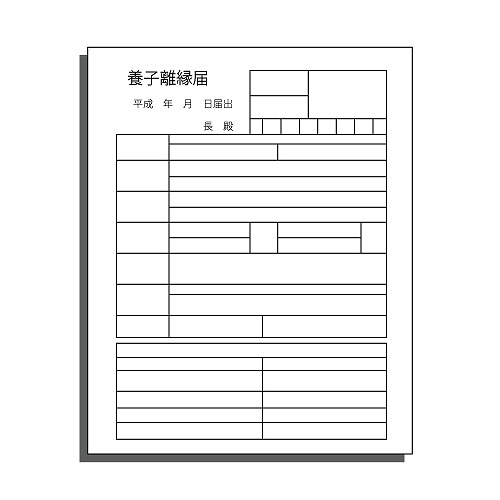離婚する夫婦が増えるに伴って、再婚件数も増加傾向にあります。また、子連れでの再婚件数も増加傾向にあるようで、子連れでの再婚の場合は子供をどうするかについても考えなくてはなりません。
婚姻届を提出すれば当事者同士は婚姻関係が結ばれますが、配偶者の子供と自動的に親子関係が結ばれることはありません。そこで、一般的に用いられるのは養子縁組という制度です。
今回は、この 養子縁組 の 手続き の方法を解説します。
意外とシンプル、養子縁組に必要なたった3つの手続き
普通養子と特別養子
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
普通養子縁組は、当事者双方に養子縁組の意思が存在し、役所に縁組の届出をすれば認められます。
いっぽう、特別養子縁組は、養親となる人が家庭裁判所に審判を申立て、その審判を経て成立します。
このように特別養子縁組は普通養子縁組と比べて、手続きが複雑で要件も厳しくなります。
どちらを選択すべき?
再婚の際の養子縁組においては、普通養子が一般的でしょう。
養子となる子供が、特別養子縁組の要件とされている年齢を超えていることが多いことが、その理由の1つにあります。また、万が一離婚したときのことを考えると、特別養子縁組をしてしまうととても面倒なことになることも、理由として考えられます。
養親と養子との結びつきが強いことが、特別養子縁組の特徴です。特別養子縁組をすると実親との親子関係は解消され、相続権も失われます。いっぽうで、離縁をすることも非常に困難になるのです。
このような理由から、再婚相手の子供とは普通養子縁組を行うのが一般的になっています。
手続きも比較的簡単で、普通養子縁組成立までの手続きは、「縁組意思の合致」「届出用紙の記入」「役所への届け出」「養子縁組の成立」の3つのみです。
縁組意思の合致
養子となる子供が幼い場合は、縁組意思の確認は法定代理人、つまり父または母が子供に代わって意思表示をすることになります。
他方で、養子となる子供が成人の場合は、養子となるかどうかの判断は本人に委ねられることになるので、本人の意思の確認が必要になります。
届出用紙の記入
婚姻届と同じように、養子縁組届には証人記載欄があります。婚姻届と養子縁組届を同時に提出したい場合は、婚姻届と同時に養子縁組届も受け取っておくとスムーズに手続きを進めることができます。
養子縁組届には証人記載欄の他、養親と実親に関することや住所・本籍地などを書く必要があります。再婚の際の養子縁組では、引越しを伴うことも多いでしょう。
引越し先と元の住所、どちらの住所を記載すれば良いのか迷うところですが、養子縁組届を提出する時点で住民票を移していないようであれば、元の住所を記載する必要があります。
書き直しや再提出などの無駄な手間も省けるので、分からないところがある場合は、そこは空欄にしておいて、窓口で教わりながら記入することをお勧めします。
役所への届け出
養子縁組届は婚姻届などと同様戸籍に関する届出なので、土日や夜間でも役所の時間外窓口で提出することができます。忙しい人にとってはとても便利なのですが、注意しなければならないこともあります。
時間外窓口では、職員届出の内容を確認してくれることはありません。届出用紙を預かってくれるだけですので、届出の内容を確認した職員から、後日問い合わせが来ることも考えられます。また、記入方法が分からなくても、時間外窓口では記入方法の指導はしてくれません。
しかし、間違っている箇所は後から訂正することができます。時間外にしか行くことができない人は、記入方法が分からなくても取り敢えず記入して提出することも可能です。
養子縁組の成立
これら3つの手続きを経れば、普通養子縁組が成立します。このように、普通養子縁組の手続きは意外と簡単なものです。
子供の将来のためにも、養子縁組の申請を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
意外とシンプル、養子縁組に必要なたった3つの手続き
普通養子と特別養子
どちらを選択すべき?
縁組意思の合致
役所への届け出
養子縁組の成立